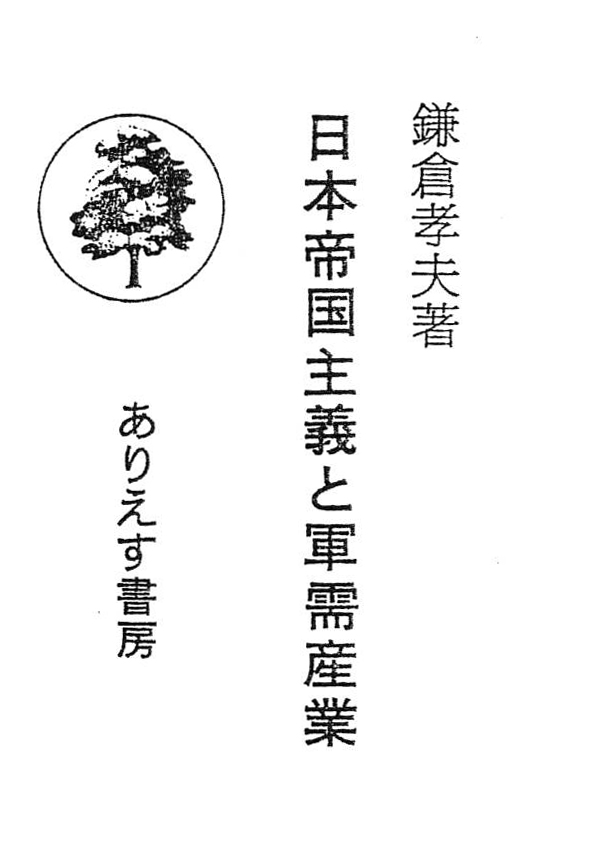日本帝国主義と軍需産業
鎌倉孝夫
ありえす書房
一六二〇円
武器輸出三原則の緩和を受け、日本の防衛産業が兵器開発に力を注ぎ始めている。防衛予算が増加していることも考えれば、日本で軍産複合体が台頭するのも時間の問題であろう。実際、国際社会では既に、軍産複合体は強大な力を持っている。例えば、アメリカがイラク戦争を始めたのも、軍産複合体の利益のためだったと言われている。
恐らくこの指摘はそれほど間違っていない。しかし、こうした事実を指摘するだけではあまり意味がない。なぜ軍産は複合してしまうのか、その点にまで踏み込まなければ軍産複合体の本質を掴むことはできない。(なお、ここでは軍産複合体とは、国家と軍需産業の結びつきのことを指すこととする。)
本書は軍産複合体についてマルクス経済学の観点から論じたものである。ソ連崩壊前に出版されたものなので、社会主義国家の存在を前提にした議論ではあるが、それを差し引いても重要な指摘がなされている。
本書に基づけば、軍産が複合するのは、ある意味で当然のことではあるが、互いに利害が一致しているからである。国家にとっては、軍需支出は有力な失業対策になる。軍需支出は巨大な財政政策であり、それにより雇用機会を創出することができるからだ。実際、ナチスドイツは不況によって社会的動揺が広がる中、軍需支出を行うことで失業を吸収し、体制を強化した(本書34頁)。
他方、軍需産業にとっては、軍事支出による需要は極めて安定的なものであり、その上軍事品の発注は企業に対する一定の利潤を盛り込んだ形で行われるため、企業は膨大な利潤を得ることができる(40頁)。
それ故、軍産複合体は、とりわけ不況の際に兵器の生産を推し進める。しかし、兵器の生産を拡大するためには、兵器が消耗しなければならない。そうでなければ、在庫が膨大に積み上がってしまう。兵器の消耗とは、言うまでもなく戦争のことである(同前)。ここに軍産複合体が戦争を望んでいると言われる所以がある。
もっとも、自国が戦争を行えば、軍産複合体も損失を被る恐れがある。彼らとしては、自らは戦争に参加せず兵器生産を拡大できた方がよい。そのためにはどうすればよいか。外国で戦争が起こればよいのである。そうすれば、兵器の輸出によって利益を得ることができる上、実害も被らなくて済む。
今日の国際社会で兵器輸出が盛んになっているのも、こうした事実と無関係ではないだろう。陰謀論者のように全ての戦争を軍産複合体のせいにするのは問題だが、戦争の陰に軍産複合体が潜んでいることは否定できない。
とはいえ、今日の世界ではかつてほどには戦争は起こらない。それ故、どうしても使われない兵器が累積してしまう。また、技術は絶えず進歩しているので、古い技術による兵器も使われずに累積される。兵器輸出は、こうした兵器を処理するためにも行われる。ロッキード事件やグラマン事件の背景にはこうした事情があったと見るべきだろう(34頁)。最近では、何の役にも立たないと言われているMD(ミサイル防衛)がそうかもしれない。
もとより、兵器輸出は「輸出」である以上、国際競争の波にさらされる。それは産業合理化を招き、結局は雇用削減、失業増加をもたらす(36頁)。安倍政権は兵器輸出によって日本経済を活性化させようとしているようだが、あまり上手くいかないだろう。
見落としてはならないのは、国家が軍需産業と結びつくのは、資本主義社会において必然的に生じる現象だということである。今回詳しく論じる余裕はないが、資本主義は必然的に恐慌をもたらす。恐慌の解決を市場に任せていては、国家は国民の反感を買い、場合によっては体制が崩壊してしまう。国家は現体制を維持するために、どうしても軍需産業と結びつかなければならないのだ。
他方、軍需産業は利益を上げるために、国家と結びつこうとする。彼らは資本主義の論理に忠実に従っているだけである。
それ故、もし軍産複合体を解体したいのであれば、敢えて言うなら資本主義をやめるしかない。資本主義を肯定しつつ軍産複合体を否定するのは不可能である。
もちろん軍産複合体を倫理的に批判することは可能だし、すべきだが、これは資本主義の構造的な問題であるため、倫理的な批判によって食い止めることはできない。
倫理的な批判により資本主義の問題を克服できると考えるのは、恐らくマックス・ウェーバーの影響(誤読)によるものと思われるが、この点についてはまた別の機会に述べたい。
(編集委員 中村友哉)