国体学への誘ひ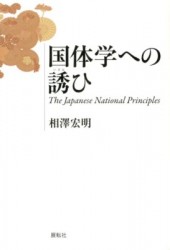
神懸的、信仰的国体論であっては広範な支持を得ることは難しく、国体擁護のためには、国体論に十分な科学性が無ければならないという里見の思いが、「科学的」という言葉に込められている。
昭和二年十二月、里見は「国体科学を提唱す」と題して、次のように国体科学を定義している。
「国体科学とは日本国体学を中枢部と為し、総合史観と国体史観とを左右の翼と為したる日本神話学、比較国体学、比較国相学、比較国性学、政治学、社会学、法律学、経済学、文明史、日本歴史、宗教哲学、各種政策等を総称する日本国体主義文化科学の一大学問叢の謂也」
昭和十一年に里見によって創立された日本国体学会は、昭和四十八年の里見逝去後も、「日本国民に国体の存在と価値を再認識させ、国体に対する科学的思想と信念とを培養して自主自尊の国民的自覚を与える」ために活発な活動を続けている。本書は、同学会理事を務める著者の相澤宏明氏が、「科学的国体学」の世界へと、読者を誘ってくれる。国体学の入門書として相応しい一冊だ。
著者は、冒頭で国体を揺るがす最近の問題点として、日本国憲法改正の遅滞とその機運の頓挫、国家主権と地域主権の矛盾と相克、皇位継承法を巡る国民間の対立、国防および領土意識の衰退と低迷、祝日の非伝統・非皇室化と祭日の消滅、地方の疲弊と地域共同体の破壊、他民族に対する排外思想の胚胎といった問題を挙げ、国体の重要性についての読者の意識を喚起する。
著者が扱う国体学に関わる今日的問題は多岐にわたるが、章ごとに内容の一部を紹介すると、まず「第一章 狂気の時代を乗り越える」では、政治家の多くが民主主義を金科玉条とし、個人主義がもたらす地球市民なる幻想や国連中心主義という偏見に惑い、人倫道徳、国家道義などといった、真の世界人類の共存共栄の方途を顧みようとしないと批判する。
「第二章 国体はいかなるものか」では、わが国では、統治者、国民、領土だけではなく、神と道という要素が国家成立要件であり、国民の本分は皇道実践の翼賛であることを強調する。ここで言う「道」(皇道)とは、天照大神の神勅に表出している道であり(32頁)、その源こそが、神であると説明される。
「第三章 国体は変化するのか」では、戦後国体が変わったとする議論に対して、「天皇[君]と国体は密接不可分である。しかし天皇の立場が改変されたとか、権限が縮小されたといふだけで国体の変更といふのは一面観でしかない」と書き、また、わが国における君臣一体、君民於道一致[道]は、少々の衝撃では崩れないと主張する(74頁)。
「第四章 国体学では時代社会をどうみるのか」では、三種の神器(玉・鏡・剣)は、皇道としての三綱(積慶・重暉・養正)実践を指し示していると指摘している。
建国の理念は、三綱を実践した上で、「八紘一宇」の実現を説いている。著者は東京裁判で検察側が、「八紘一宇」が軍事的侵略思想であることを立証しようとしたが、判決でそうした主張が退けられた経緯を説明した上で、次のように書いている。
「戦後体制を打破するためと、現今のグローバリズムに向かひ合ふためにも、今こそわれわれは八紘一宇の意味を見つめなほし、現実の社会体制の是正に邁進したいものである」(122頁)
「第五章 時代社会は権力が取り仕切る」では、「基本社会の中心にまします天皇を仰ぎ、一君万民の姿を大切にし、君民一致の精神を持つ政治家および政党を出現させることこそ、国体主義者を自認する者に課せられた責務である」と訴える(146頁)。
「第六章 日本国体学を学び実践するための方法論」では、国体を国そのものととらえず、人間生活の中において国体を体感、実感すべきだと説き、国体学は観念の所産ではなく、国民一人ひとりの生命の中に根を下し、われらの生活と直結し、実践化した世界で把握される学問であると強調している(177頁)。
日本国体学の実践の一例として、著者は昭和の日の制定運動を挙げる。昭和天皇の崩御後、天皇誕生日(戦前は天長節)であった四月二十九日は、「みどりの日」と命名され祝日として残されたが、これでは国体とは繋がらないし、国体意識の涵養に役立たないのみか、逆に戦後のわが国の悪弊と思われる戦後民主主義的祝日になり下がってしまうという思いからこの運動は展開され、平成十七年に昭和の日と改名された。
なお、著者は展転社創設者でもあり、本書は同社創立三十周年記念出版として刊行された。(編集長 坪内隆彦)
